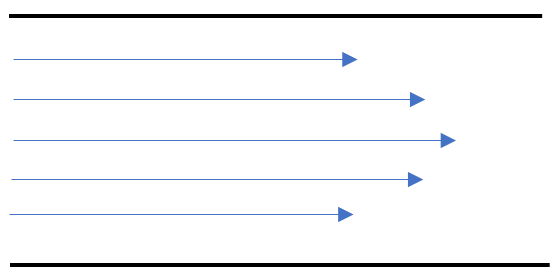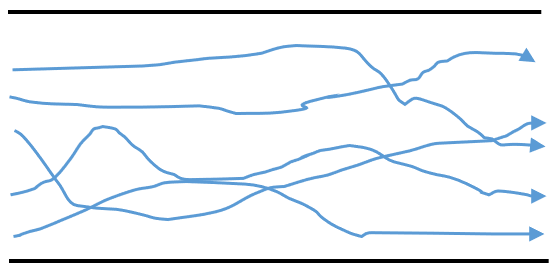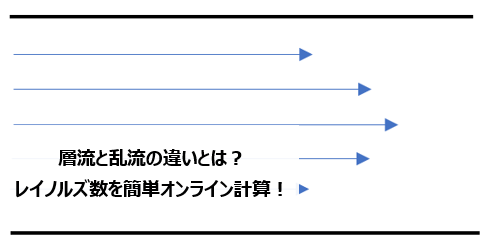層流と乱流の違いとは?レイノルズ数を簡単オンライン計算!
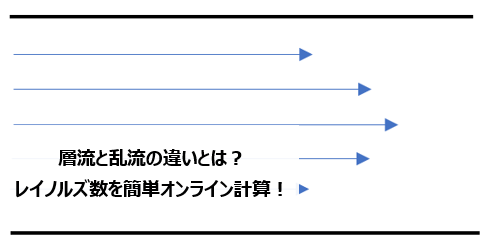
流体力学において重要な概念のひとつが「層流」と「乱流」です。配管設計や化学工学、さらには医学や空調など幅広い分野で登場する基本ですが、その違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、層流と乱流の特徴・判定方法をわかりやすく解説し、さらに実際の応用事例まで紹介します。
目次
層流と乱流の基本的な違い
層流(Laminar flow)

- 流体の分子が規則正しく層をなして流れる
- 流れは滑らかで、速度分布は放物線状
- 摩擦損失が小さいが、混合や拡散は起こりにくい
乱流(Turbulent flow)

- 流体の分子が不規則に渦を巻きながら流れる
- 速度分布はほぼ一様に近くなる
- 摩擦損失は大きいが、混合が活発で熱・物質移動が促進される
レイノルズ数による判定
層流か乱流かは レイノルズ数(Re) によって判定できます。
\(Re = \frac{ρ v D}{μ}\)
- ρ:流体密度
- v:流速
- D:代表長さ(通常は管径)
- μ:粘度
🔹 判定基準
- Re < 2,000 → 層流
- 2,000 ≦ Re ≦ 4,000 → 遷移領域
- Re > 4,000 → 乱流
🔧レイノルズ数計算ツール