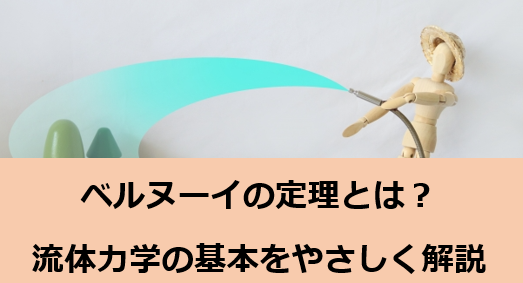ベルヌーイの定理は、流体(液体や気体)の流れにおけるエネルギー保存則を表す基本的な法則です。日常生活では、水道の蛇口や飛行機の翼の原理など、さまざまな場面で応用されています。
目次
ベルヌーイの定理の式
流体が非粘性(粘り気のない)で、摩擦や外力が無視できる条件下で、ある流れに沿って流体のエネルギーを考えると、次の式が成り立ちます。
\(P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{一定} \)
- P:流体の圧力(Pa)
- \(\rho\):流体の密度(kg/m³)
- v:流体の流速(m/s)
- g:重力加速度(9.81 m/s²)
- h:基準面からの高さ(m)
この式は、単位体積あたりのエネルギーの合計が一定であることを意味しています。
式の意味を分解すると
ベルヌーイの定理は大きく3つのエネルギーに分けられます。
- 圧力エネルギー P
- 流体が持つ押す力。
- 水道管の中の水が管を押す力がこれにあたります。
- 運動エネルギー \(\frac{1}{2}\rho v^2 \)
- 流体の流れの速さに応じたエネルギー。
- 流速が速いほどこの値は大きくなります。
- 位置エネルギー \(\rho g h\)
- 高さに応じたエネルギー。
- 高い位置にある水は落下して運動エネルギーに変わります。
ベルヌーイの定理の応用例
水道の蛇口
蛇口の出口が細くなると、水が速く流れます。
ベルヌーイの定理により、流速が上がると圧力が下がることが説明できます。
飛行機の翼
翼の上面は曲線があり、下面よりも空気が速く流れます。
流速が速くなると圧力が下がるため、翼に揚力が生まれます。
揚力については下記の記事で解説しています。
あわせて読みたい
ベンチュリ管
流体の流れる管の断面を狭くすると流速が上がり、圧力が下がります。
この圧力差を利用して流量計測や液体の吸引などに使われます。
注意点
- 粘性が無視できる流体を前提にしています。現実の流体は摩擦(粘性)があるため、完全には成り立ちません。
- 流れが層流であることが前提です。乱流ではエネルギー損失が大きくなるため補正が必要です。
まとめ
ベルヌーイの定理は、圧力・流速・高さのバランスを示す法則で、流体力学の基本中の基本です。
- 流速が上がると圧力が下がる
- 高い位置にある流体は運動エネルギーに変わる
- 航空、給水、計測など幅広い分野で応用される
簡単な水道や翼の例を思い浮かべると、理解がぐっと深まります。