流体力学や配管設計では、粘度や動粘度といった物性値が欠かせません。これらは流体の流れやすさを示す重要な指標であり、圧損の大きさにも直結します。ここでは、それぞれの意味と違いを整理し、圧損との関係を解説します。
目次
1. 粘度(絶対粘度)とは?(粘度の目安付き)
粘度(Viscosity)とは、流体の「ねばりけ」を表す物性値です。流体が流れるとき、分子同士が摩擦のような抵抗を生じますが、その大きさを数値化したものが粘度です。
- 記号:\(\mu\)
- 単位:Pa·s(パスカル秒) または N·s/m²
例:
- 水(20℃):約 1.0 × 10⁻³ Pa·s
- 空気(20℃):約 1.8 × 10⁻⁵ Pa·s
- 蜂蜜(20℃):数 Pa·s 以上
粘度が大きいほど、流れにくい(抵抗が大きい)流体です。
その他の粘度については、下記のグラフのようになっています。
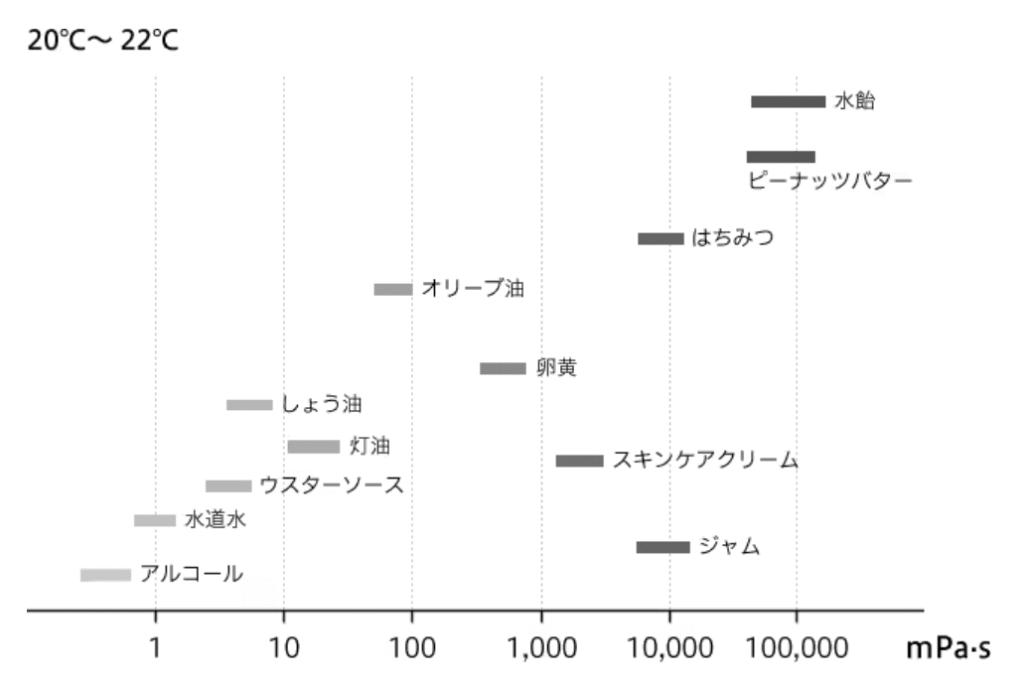
参考:キーエンスHP
詳細の値については、下記のリンクにまとめました。
ご覧ください。
工学計算ツール集
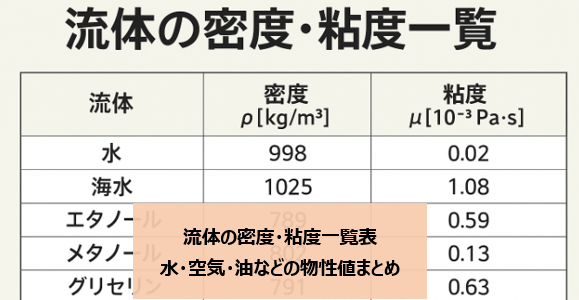
流体の密度・粘度一覧表|水・空気・油などの物性値まとめ 流体の密度と粘度の一覧表を掲載。水・空気・油・ガソリン・エタノールなどの代表的な流体について、温度や圧力の標準条件における密度[kg/m³]と粘度[10^-3 Pa・s]をまとめ...
2. 動粘度とは?
動粘度(Kinematic Viscosity)は、粘度を密度で割った値です。流体の「流れやすさ」をより直接的に表す指標です。 \(\nu = \frac{\mu}{\rho}\)
- 記号:\(\nu \)
- 単位:m²/s
例:
- 水(20℃):約 1.0 × 10⁻⁶ m²/s
- 空気(20℃):約 1.5 × 10⁻⁵ m²/s
ポイント:動粘度は、流体の種類や温度で変化しますが、密度を考慮しているため「同じ条件でどれくらい拡散・流れやすいか」を比べやすい値です。
3. 粘度と動粘度の違い
| 項目 | 粘度(μ) | 動粘度(ν) |
|---|---|---|
| 定義 | 流体の「ねばりけ」そのもの | 粘度を密度で割った値 |
| 単位 | Pa·s | m²/s |
| 影響要素 | 温度 | 温度 + 密度 |
| 利用場面 | 摩擦損失の計算、ポンプ設計 | レイノルズ数、圧損評価 |
4. 圧損との関係
圧損を評価するとき、流れが**層流(Re < 2000)か乱流(Re > 4000)かを判断する必要があります。
その基準に使われるのがレイノルズ数(Re)です。
\(Re = \frac{VD}{\nu} \)
- V:流速 [m/s]
- D:管径 [m]
- \(\nu \):動粘度 [m²/s]
レイノルズ数が小さい(動粘度が大きい)ほど層流になりやすく、摩擦損失は流速に比例します。逆に乱流では流速の二乗に比例するため、粘度や動粘度は圧損の計算に直結する重要な物性値です。
レイノルズ数計算ツール
レイノルズ数を簡単に計算できるツールを用意しました。
下記の記事をご覧ください。
工学計算ツール集
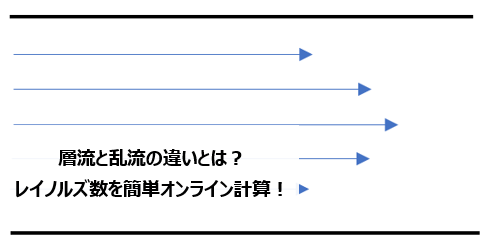
レイノルズ数計算ツール|層流・乱流判定を簡単にオンライン計算 管内流れの層流・乱流を、流速・流量・管径・流体を選ぶだけで簡単オンライン計算。20℃・1気圧の標準状態を基にレイノルズ数を表示。エンジニアや学生にも分かりやすいツー...
5.圧損の計算ツール
様々な圧損の計算の仕方や、便利な計算ツールについて解説しています。
下記の記事をご覧ください。
工学計算ツール集
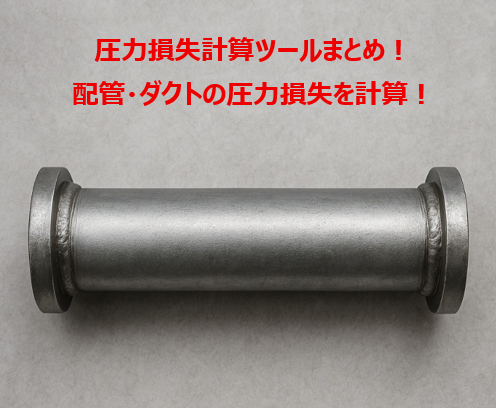
圧損計算ツールまとめ|直管・曲管・オリフィス・入口出口 直管・急拡大縮小・曲管(エルボ・ベンド)・オリフィス・入口出口の圧損を自動計算できる無料ツールをまとめました。損失係数Kと圧力損失ΔPを簡単に算出可能。
6. まとめ
- 粘度(μ)は流体の摩擦抵抗を表す
- 動粘度(ν)は粘度を密度で割った「流れやすさ」
- 圧損計算では、動粘度を用いてレイノルズ数を求め、流れの状態(層流/乱流)を判断する
- 流体の種類や温度で大きく変わるため、設計時には正確な物性値が必要

